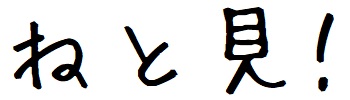銭湯図解
塩谷歩波
出版社:中央公論新社
発売日:2019/02/20
大学院で建築学を修め、設計事務所での勤務経験もある著者による銭湯の図解本。都内を中心に全国23の銭湯が紹介されている。
綿密な実測データに基づいて描かれた臨場感あふれる俯瞰図には、それぞれの銭湯の特色やお風呂の種類、タイルの柄やお湯の温度に至るまで、事細かな情報がぎっしり書き込まれている。
昨今、ネット上でもにわかに銭湯ブームがきているような感じがしている。アパートや戸建てを問わず、一般的な家庭のお風呂というとどことなく手狭な感じがするもの。一方、観光地のホテルなどの大浴場だと、どこか非日常的なイメージが強い。その点銭湯となると、身近なところで広々とした湯船に浸かれる、日常生活の延長線上にある癒しの空間、そんな感じがしないではないか?
私も都内住のころ、近場にある銭湯によく通っていた(そこは数年前に閉店してしまった)。夕暮れ前、まだ陽が高い時間帯に入る一番風呂の気持ちよさは、他のなにものにも代え難い。
著者は設計事務所勤務のころ、休職を余儀なくされた時期があったという。その時、心身の疲弊を癒してくれたのが銭湯だった。そこから銭湯の魅力にとりつかれ、今では、イラストレーターのほかに銭湯の番頭として働いているという。正直ハマりすぎている感が否めない。
しかし、銭湯はそこまで人を引きつける魅力をもった場所だ。本書には、その魅力がたっぷりと詰まっている。
ひとつ注文をつけるとすれば、もう少し大きければよかったと思う。A5版ではせっかくのイラストも小さくなってしまっている。
あ、これはイラストの多くが女湯だからではない。
ヒトは「いじめ」をやめられない
中野信子
出版社:小学館(小学館新書)
発売日:2017/09/28
脳科学者・中野信子先生による「いじめ」論。正直、タイトルが衝撃的すぎる。
個人的見解として、どうしてもいじめは起こってしまうものだと思う。それは人間が人間としてある以前に、生物として本能的な部分でそうした要因を持ち得ているのではないかと考えているからだ。
人間は"社会"という集団を構築することで、自然界を生き延びてきたという感がある。ゆえにその調和を乱す要因を排除しようという心の動きが、どこかに潜んでいるはずなのだ。
本書では、そうした根元的な部分への解明が、脳科学の視点から科学的に綴られている。専門用語も飛び交うが、的確な解説がふされているので臆することはない。
新書ということもあって、若干ゆるみのある文章だが、格式だった堅さが抜けた感じで読みやすいともとらえられる。
個人的には、今まで考えていたことを科学的=再現性のあるかたちで示してくれたという安堵感がある。
しかし大切なのは、「いじめをやめられない」からあきらめるのではなく、そこにどう対処していくべきかを考えることだ。
本書後半では、そうした対応策、あるいは提言がなされているが、そこだけ読んでも十二分に意義があると思う。
≪関連図書≫
いじめの構造
なぜ人が怪物になるのか
つまずきやすい日本語
飯間浩明
出版社:NHK出版
発売日:2019/03/25
「三省堂国語辞典」編集委員がおくる「つまずきやすい」日本語論。
「間違えやすい」ではなく「つまずきやすい」というところに妙がある。このことに関しては本書の冒頭でその意が記されているが、読んでみて「なるほど!」と腑に落ちた。
言葉は常に変化し続けるもの。
いわゆる流行語をはじめ日頃使っている言葉でさえ、数年経てば使われなくなったりあるいはその意が変化したり、実に変幻自在。
幸か不幸かそれが言葉のもつ宿命のような気もするが、日本語においてのそのきっかけを、著者が明治期の「言文一致」に求めたのにはとても共感した。
日本語には従来、話し言葉と書き言葉を明確に区別する節があった。話し言葉のそれは、その時代その時代においてさまざまに変化する一方で、書き言葉は古来よりほぼ違うことない姿をとどめていた。
それが明治期の「言文一致」をもって区別されることがなくなって以降、話し言葉も書き言葉も、同一の言葉として扱われるようになった。つまり、同様に「変化するもの」となったのだ。
ジェネレーションギャップという言葉がある。2000年以前なら「10年ひと昔」などとも言われていたが、以降ではもっと小刻みに時代の流れを区分せざるをえない感がある。インターネットをはじめとした発信媒体の拡充によって、そのスピードはますます速まっている。
当然それは言葉についても逃げ切ることができるものでもなく、むしろメールやSNSといった媒体の多くが言葉に依存しているのだから、その影響を直接受けているようなものだ。
よくテレビ番組などで、「言葉の乱れ」「間違った言葉遣い」といったテーマが取り上げられるのを見るようになって久しいが、そう考えれば、言葉が「乱れ」たり「間違っ」てしまうのも当然のことなのだ。
しかし本書では、それを「つまずきやすい」と表現している。時代が変われば人の認識も常識も変化する。それはなにも言葉そのものが変化しているのではなく、そうした表面的な部分の変化であって、その底流にある言葉そのものの変化ではないはずだ。
だからこそ、表面的な言葉の表面で「つまず」くことが多くなっているだけなのかもしれない。
日頃、「言葉使いがどうのこうの」「変な言葉ばかり使って」などと小姑のように口やかましく言われている人にとっては、ある意味救われる一冊かもしれない。
本書はそうした言葉の変化、使い方の誤用のすべてを肯定しているわけではない。ただ、「言葉」のもつ力をもっと広い視点から見つめ直そうとしているのだと感じた。
承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱
坂井孝一
出版社:中央公論新社(中公新書)
発売日:2018/12/19
日本中世史の一大事。政治の主力が、それまでの天皇を中心とした公家社会から幕府を中心とする武家社会へ移行するきっかけとなった、「承久の乱」。
日本史を学んだ人には聞き覚えのある戦乱だろう。乱よりもむしろ、首謀者たる後鳥羽上皇、そしてその子息である順徳・土御門の三上皇が島流しとなったことの方が印象強いだろうか?
昨年末から今年にかけて、下記参考図書含め、承久の乱がらみの新書が2冊立て続けに出た。
私自身、10年ほど前から定家・実朝という後鳥羽上皇に関連のある人物を追いかけ、また昨今は渦中の後鳥羽上皇本人についても調査・研究を進めていただけに、こうして新書が出たことに驚きを隠せない。
承久の乱自体、当時の鎌倉方の威勢をはばかってか、公家の日記はじめ公文書の類も残っていない、あるいは隠蔽されており、一次史料と呼ぶべきものが皆無である。自然、軍記物を中心とする二次史料にその史実を依拠せざるを得ないという部分を大いにもっている。
それゆえ明治以降、本当の意味ではじまったともいえる後鳥羽および承久の乱の研究が、賛否両論のまとまりのない形を描きながら進んできたとも言える。
読んだ限りにおいて、本書は戦後、特に昭和末から現在にいたる研究成果を、従来の通説とされてきた「承久の乱」像に当てはめ再考しようと提言しているように思う。
本書で示されている最新の研究成果というのも、私にとっては自分の調査・研究のなかで既知のものばかりだったが、こうして改めて問い直そうとする姿勢の本書を、在野ながら一研究者として評価したい。
……以下余談となるが、下の参考図書にあげるもう一つの新書に関しては、正直読む価値なしと個人的に思っている。巷では大いに売れているようだが、いくら新書とはいえ歴史関係の書物に参考文献の一つも付されていないというのはいかがなものか。この先生に関しては毎度のことなのでさして驚かないが。
何より、学者の書いたものとは到底思えない文章と内容には辟易するばかりだ。
≪参考図書≫
承久の乱 日本史のターニングポイント