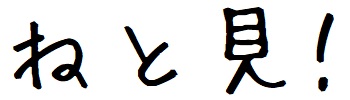なぜ世界は存在しないのか
マルクス・ガブリエル 著 清水一浩 訳
出版社:講談社(講談社選書メチエ)
発売日:2018/01/13
2013年、哲学の本場ドイツで出版されるや否や異例の大ベストセラーとなった哲学書。本年1月になってやっとその邦訳が出た。Amazonのページを見てもすでにベストセラーとなっている。
著者はドイツ史上最年少で哲学教授に就任した新進気鋭の哲学者マルクス・ガブリエル。哲学に多少興味のある人ならすでにその名を聞いたことがある人も多いだろう。
ポストモダン以降の世界の哲学界において、
・自然主義的転回
・メディア技術論的転回
・実在論的転回
という3つの大きな潮流があるが、ガブリエルはその中で、ポスト言語論的転回として際立った存在感を示す実在論的転回の中心的人物の一人として活躍している。
彼の提唱する「新実在論」では「世界=あらゆるものを包括する全体」という視点が置かれているが、これは構造主義の行きついた先のポストモダンへの真っ向な批判の礎、物事を様々な側面からとらえ多様に理解しようとする流れを乗り越えるための足掛かりなのだ。なぜそうした必要があるのか? もちろん多様な視点から物事をとらえるということ自体に共感できる人は多いはずだが、これはややもすると相対主義に陥る可能性がある。つまり見方次第でどうとでもいえるようになってしまうのだ。
自分たちが普段目にするニュースなどを考えてみてほしい。メディアを背後に隆盛するポピュリズム、たとえばある国が戦争を起こす理由として掲げる「大量破壊兵器の存在」、これは現実に存在しなくても言い方次第で存在しうることになってしまう。
神の視点ではないが、唯一の世界という現実を多様に見定めた結果、現実とはかけ離れた世界像を我々は眺めてしまう。そしてその世界像を現実としてとらえてしまう危険性を孕んでいることに気付ける人はどれほどいるだろうか? ガブリエルのいう「新実在論」はこのことへの警鐘といってもよいと思う。
「新実在論」において、現実に「存在」するということは「意味の場に現象」することととらえられているが、この「意味の場に現象」するということは、たとえばA国とB国という2国がお互いの正義を主張し戦争をはじめたとして、“A国の正義”という意味と“B国の正義”という意味がそれぞれに「意味の場」として実在していると言い換えることができる。そうすると、“A国の正義"も現実であり“B国の正義”もまた現実なのだ。両国の主張を眺める中で、我々はその両方の「意味の場」を行ったり来たりしているにすぎないのだが、それこそ自分たちが生きている現実に他ならない。そしてその「意味の場」は現実を認識する一人ひとりが持っているわけだから、多様で重層的な「意味の場」は無限にあるといえる。そして我々はその「意味の場」から「意味の場」へ不断に移行しているにすぎないのだ。ではそれを包括する「最後の意味の場」としての“世界”は、果たして存在するのだろうか? それは本書を読んで考えてみてほしい。
最後に、こうした視点に立つと、今世界に蔓延する科学主義的なものでさえ、やはり「意味の場」のひとつにすぎないことがわかるが、ガブリエルの主張の矛先はこうした科学主義的一元論への猛烈な批判にあることが、本書からは十二分に伝わってくる。
さて、あなたならどう考えるだろうか?
 〔原書〕Warum es die Welt nicht gibt |
 いま世界の哲学者が考えていること |

エロマンガ表現史
稀見 理都
出版社:太田出版
発売日:2017/11/02
今年3月、北海道で本書が有害図書に指定された。
羅列でもその告示のなされた文書のPDF版のリンクを貼ったりしたし、かなり批判めいたコメントをしたりした。
本書は今までアングラ的・腫れ物的な扱いだったエロマンガの表現方法について、大真面目に考察・研究された立派な研究書だ。
私としては、そんな書物に対してこうした指定を下すのはあまりに行き過ぎているのではないか? しっかりと内容に目を通し理解あるいは議論がなされたのか? と疑問に思うばかりなのだ。
そもそもこの指定を下す議論自体が非公開という扱いなので、道からは「男女の性的行為を露骨に描写した場面は多数引用されている」という説明しかなされていない。
確かに本書に掲載されている性交に関するコマ数は多い。同人誌にしたら何冊分になるのだろうと思ってしまう。“健全な”精神構造をもった血気盛んな青少年に対して「有害」と言いたくなるのも理解できる。
だが、そうしたビジュアル的な側面だけで青少年にはふさわしくないと判断してしまうのはいかがなものかと思うのだ。そこに何が書かれ、どう考察・研究されているのかが本来なのだから、その是非に寄らず「有害」の指定をしてしまっている点、あまりにも安直なのではと思う。
また、『北海道青少年健全育成条例に基づく有害指定』などを見て疑問に思ったのだが、こうした指定に関し、諮問にかけた書物は全て有害指定がされているし、そもそも諮問機関への該当書物の選定基準があまりにも不明確だ。これは見方によっては、恣意的な意図が働けばこの指定自体を自在にコントロールすることもできうるのではと考えるのは極端だろうか?
誤解がないように言っておきたいのだが、私はなにもこうしたアングラ的ないわゆる“キワモノ”を擁護するために言っているのではない。
有害図書指定されたとしてもそれは発禁ということではないのだから、本来的な意味での規制とまでは言い切れないと思う。しかし、この国はこうした有害図書に関わらず、規制ということに対して何ら躊躇しない姿勢が時折垣間見える。例えばユッケについても、日本でその提供を規制したとしても、海外へ行けば日常的に食べられているのであって、なにを問題に規制しているのかはなはだ疑問だ。「臭いものには蓋」という言葉通り、規制することでその場は一度収まるのかもしれないが、問題の根本的な部分を解決せずに放置しているに過ぎないのではないか? そうして規制の網目がいたるところに張り巡らされた結果、今日本全体を覆う閉塞感というか何事にも不寛容な空気が生み出されているのではないかと考えてしまう。
わが半生
W・チャーチル 著 中村祐吉 訳
出版社:中央公論社(中公クラシックス)
発売日:2014/10/09
唐突だが私は太宰治が嫌いだ。もちろん大半の作品は読んでいるのだが、どうにもあの文章のテンポが合わない。また彼の語ることが生理的に受け付けない。
しかし随筆『津軽』を読んだ際、「あ、太宰ってこんなヤツだったんだ…」とかなり好感をもって見直したという経験がある。
このW・チャーチルに関しても然り。偏屈そうな顔をしてたかと思うと満面の笑みで「Vサイン」をしていたり、父の本棚にあった本を繰ってそんな写真を目にしているうちに、私は写真や動画に写る際、いわゆる「ピース(Vサイン)」をすることをどうにも毛嫌いするようになった。これは幼稚園の頃の話しなのだが、それ以来一切していない。と同時にチャーチル自身に対してもかなり悪しきイメージしかもっていなかった。
W・チャーチル――第二次世界大戦中のイギリスの首相にして、「現代のもっとも偉大なイギリス人」と称された彼の存在は、20世紀の世界史屈指の要であったことは過言ではない。
本書はそのチャーチルが政治家として活動しはじめるまでの半生を語った自伝だ。政治家にありがちな自尊心に満ちたプロパガンダ的なエッセイとは違い、ユーモアにあふれたかなり砕けた日記風の文体が、とても好感触だった。ノーベル文学賞をとっただけの文才を認めざるをえない。
落第生として過ごした学生時代、軍人となってからのさまざまなエピソード、ジャーナリストとしての活躍など、今まで知ることのなかったチャーチルのアクティブな性格を読み取ることができた。第二次大戦下において下したさまざまな冒険的英断は、政治家というよりも冒険者そのものだったからこそなしえたことのように思う。
いままで食わず嫌いのように対していた私だが、意外にも見る目が変わったと言わざるを得ない一冊となった。
曲線の秘密 自然に潜む数学の真理
松下泰雄
出版社:講談社(ブルーバックス)
発売日:2016/03/18
kindle版
数学という学問の中でも屈指の美しさを誇る「円」。それを少し変形することによって現れる楕円。
この円と楕円をめぐる物語を一たびめくれば、古代ギリシャを発端とした2000年超の悠久の歴史を紐解くことになる。
本書は円、特に楕円及び楕円曲線を中心トピックスとした科学史でありながら、曲線に関する基本的な考え方も学べる良書だ。
円から楕円への変遷に関しては、ケプラーやガリレオといった天文学の雄のエピソードを交えつつ、どのように考察されていったかが実にわかりやすかった。またそこから敷衍して、正確な時を刻む時計の開発に至る科学者たちの試行錯誤する姿は重要だ。
当時にあって困難を極めた曲線の周長計算も、今の時代では微積分を用いて容易に計算できる。しかし、著者はそこで「(計算が困難だったことに対し科学者たちの)突破口を開いたのは『探求心』だった」と言う。確かに、数学に限らず現代社会ではいろんなものが便利に利用できているが、その一つひとつが先人たちの試行錯誤や努力といった歴史を担っている。そしてそれを推進したのは紛れもなく「探求心」だったのだろう。
本書後半ではこうした歴史的変遷の先にフェルマー予想解決へ至る道筋が示されている。
1996年にワイルズによって証明されて以降は“定理”となっているが、それがまだ予想だった頃、証明への最後の鍵を握ったのが本題にもある「曲線」だった。フェルマーの最終定理に関しての解説本など多数出ているものの、文系の人などにとってはどうしても難解だったりするのだが、本書での解説は(細かい事項が省かれていたりもするが)十二分に咀嚼された上で実にわかりやすいものになっている。
昨今のブルーバックスでも「わかりやすく」て「読みやすく」て「面白おかしく」解説しているものを度々目にするようになり個人的にちょっと残念に思っていたりもしていたのだが、本書は難解で敷居が高そうに見える分野のことでも「(レベルを下げることなく)わかりやすく正確に」解説するというブルーバックス独自の精神性をしっかりと貫いている感を受けた。
 |
 数学ガール2 フェルマーの最終定理 |