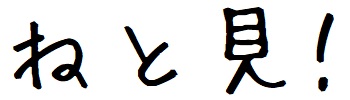土と内臓 (微生物がつくる世界)
デイビッド・モントゴメリー, アン・ビクレー 著 片岡 夏実 訳
出版社:築地書館
発売日:2016/11/12
地質学者と生物学者の夫婦による共著。本書はこの学者夫婦が新居の痩せ細った庭の土(正確には「死んだ土」)を掘り返すところから始まっている。コーヒーがらや木くずなど、ほぼ出しガラのような有機物を入れただけなのに、その土にはたちまちさまざまな生命が息衝いた。……しかしそれはなぜ起こったのか? 本書の原題『The Hidden Half of Nature(自然の隠された半分)』に、そのヒントが紛れもなく隠されている。
本書は土中の生物、殊、細菌などの微生物が、いかに私たち人間の生活を含めた自然界の生態系全体に大きく寄与しているかを教えてくれる専門書だ。
「ヒトの消化管を(トポロジー的に)ひっくり返すと植物の根と同じ働き」をするという見解に至った著者は、植物が土中から栄養源を得る働きと人間が消化器官で栄養源を得るための働きが、いずれも微生物による活動が重要な役割を果たしていることを伝えてくれる。
土中より微生物の力を利用して栄養素を集めた植物を、動物が摂取することでその栄養素を吸収し、そしてその排泄物あるいは死骸が再び土中で分解されることで次の栄養素となる一つの循環。生態系のそうした一連のサイクルを可能にし、また最大の功績をもたらしてくれるのが他ならない細菌類をはじめとした微生物だ。それはつまり、生命の土台ともいえる存在に他ならない。
本書中、近年の人類が直面する疾患について、かつては感染症などが主だったところに代わって近年は慢性的な疾患が増えていることを指摘している。著者はその原因を、食生活はじめ日常生活の多様な変化、あるいは遺伝子の変異という一般的な見解では説明できないとし、私たちヒトの体内のマイクロバイオーム(微生物の集合体)の急激な変化によるものと結論づけている。感染症を克服しようと抗生物質を使用する過程で、体内のマイクロバイオームにもダメージを与えていたというのだ。
これは土中から栄養を得る植物を巡る環境、特に農業の在り方へも同様に指摘されている。化学肥料を用いることでその収量を容易に増やすことが出来るようになった一方で、植物の根に定着する菌の数は減少し土中のミネラル分が次第に乏しくなっているという。結果、植物→動物→土という一連のサイクル全体のもつエネルギーをだんだんと弱めてしまうことになる。
本書はそれらを踏まえたうえで、自分たちの代謝の重要な部分を担う微生物をもっと見直そうと結論づけている。微生物の世界に目を向けることは、自然の中ではたらいている生態系全体を見ることであると同時に、一個の生物である自分を見ることに繋がるというメッセージだ。
私も普段、農業をもっぱらの仕事としていて思っていることなのだが、農業自体を資本主義の枠組みに組み込んでしまうのはとても残酷なことだ。そこではどうしても生産効率をあげ、経済循環に沿う形をとらなければ途端に行き詰まってしまう。しかし方法はいっぱいあるはずなのだ。自然をコントロールすることで生産効率を上げられるのなら、そのコントロールを素直に移行して、自然の仕組みや循環をうまく利用することで生産効率を上げられるのではないか? もっとも日本のように作付面積も猫額な国にあっては、周囲の農家との兼ね合いも出て来てしまうので独断でそうした農法を行う訳にはいかない部分もあるが、しかし、これは近々に改善の求められている話しであることを農家含めその関係者は認識しておかなければならない。
【関連書籍】
土の文明史
コックリさんの父 中岡俊哉のオカルト人生
岡本 和明, 辻堂 真理 著
出版社:新潮社
発売日:2017/08/18
表題にある「中岡俊哉」という名前を見てピンと来た人はいるだろうか?
1970年代を皮切りに日本中を席巻した超常現象・オカルトブームの火付け役。世間にそれらを認知させた功績は、戦後の日本文化を語る上で欠かせない。
私は昭和の終わりに生まれたが、それでも幼心に超常現象を特集したテレビ番組を盛んにやっていたのを目にした記憶がある。また一時期は、『トイレの花子さん』や『木曜の会談』といったテレビ番組もやっていたから、本書で語られる当時の影響を少なからず受けて育ってきた部分がある。とはいえ「中岡俊哉」と聞いてすぐに了解できたわけではない。「そういえば友達がもってた心霊写真の本で見かけたような……」そんな状態だ。
なぜ氏が超常現象・オカルトといったジャンルを"研究"するに至ったのか、そのきっかけまでの半生が語られるところから本書は始まるのだが、すでにその時点で面喰ってしまった。あまりにも壮絶で数奇な半生。人類の歴史上においてもかなり衝撃的な出来事の渦中に自ら飛び込んだといっても過言ではない青春時代。家庭をもった後も、時代に翻弄されているように見えてその実自ら道を切り開いて行ったと思える足跡。具体的な内容は本書に譲るが、そこで磨かれた人間性は後にブームの最中にもその誠実な姿として立ち現われているように感じた。
日本において、超常現象やオカルトといったジャンルは未だにどうにも胡散臭い雰囲気で語られる節がある。やはり一時期、警察捜査などにも協力する海外の霊能者や透視能力者などを日本に招き、国内の未解決事件にあたってもらうという内容のテレビ番組が盛んにつくられるようになって、そうした雰囲気も若干和らいだ風はあるが、どこか根深く尾を引きづっている感は否めない。
「七疑三信(7割疑って3割信じる)」をモットーとする氏の超常現象研究家としての真摯な実証検分は、ゴールデンタイムのセンセーショナルなテレビ番組には打ってつけではあったものの、その反面、週刊誌による揚げ足取りとも思える痛烈な批判が軒並みゴシップ好きの国民性を煽った。
超常現象、超能力……それらは本当にこの世にあるのか? 果たして真相はどこにあるのか?
途中、稀代の透視能力者とのやりとりの中で、中岡の寿命が指摘されている場面がある。後年その死を前にして、中岡は今まで蓄積していた映像・写真を含めた膨大な資料の処分を指示していた。これらが意味するもの、そしてその最期がどのような結果であったかは、本書を読んでみて考えて見て欲しい。
著者の一人岡本和明氏は、中岡氏の御子息だ。
当初、周囲からの勧めに反し父親の本を書くことに乗り気ではなかったようだ。しかし、岡本氏をしてしか描ききれなかった中岡俊哉の姿は、とても自然体で身近にいた人かのような感じを受ける。身内が身内のことを描いた本には、時に贔屓目であったり自尊心が垣間見れるようなものがあるが、本書にはそんな気負いが一切感じられなかったことにとても好感が持てた。
平成の終わり。新たな時代を迎える前に、一時代を築きあげた人物のこうした伝記が出されることは非常に意味深いことだと思う。
朝鮮思想全史
小倉 紀蔵
出版社:筑摩書房(ちくま新書)
発売日:2017/11/08
この手の本を手にした時、必ず本当に「"全"史なのか?」と疑ってしまう。メジャーな国やジャンルのものならば、「この辺りはあまりにも有名だから省いてしまおう」あるいは「ここは人気のある部分だからページを割こう」という魂胆見えみえののものが多く存在するのは事実。だが本書においては本当に"全史"だった。
私も学生時代の専攻がインド哲学・仏教学だったこともあり、特に日本仏教を探究する上では中国仏教はもとよりその地に根付く思想史をあまねく学び取らねばならないが、朝鮮半島のその歴史もまた然りなのだ。しかし、本書ほど朝鮮半島における思想史を網羅的概観的に且つ時代間の変遷を踏まえてまとめられたものを他に見たことがない。また思想史を背景とした文化的側面、現代の半島情勢に潜むその思想的な根拠にまで言及している姿勢には瞠目させられた。
日本の思想史あるいはその文化的な営みを語る上で、外部から到来する文化に対する性格として松岡正剛の言を借り「ブルコラージュ(修繕)的な包摂法を取る傾向が強い」と冒頭で書いているが、それは即ち、日本という国がこれまで培ってきた文化的思想的背景を探る上で、その"輸入先"の背景を知ることはかなり重要なことだと言うことと同義だ。それはある意味で"輸入先"で成熟した哲学が成立した結果、受容した日本の側でそれらしい画期的な哲学的思索が必要なかったという推測もできうるという結論を得るのだが、これを語れば長くなるので別の機会に譲りたい。
なにはともあれ己を知るためにその範を学ぶことは重要にして有意義である。
いつだったか、日本という国の文化的成立に関し、「大陸という母体から、中国という乳房を介し、朝鮮半島という乳首をもって日本はその母乳を得た」という表現をした人の言葉を聞いたことがあるが、本書一読後にその感を改めて感じざるを得なかった。
読んでみての本書の難点ももちろんある。
まず、時代あるいはジャンル別に参考文献が豊富に掲載され人物についての索引も多いが、その反面、用語についてのものはほぼ皆無と言って良い。もちろん多くのものは本文中で詳しく解説されているが、思想史を語る上ではそのキーワードを拾い上げていくのもまた必要な観点だ。
そして、冒頭でなるべく「著者個人の解釈を排除」し「客観的な事実」を述べたいとしているが、これもまた聡明な著者をしても不可能なことだ。ある特定の地域や時代を誠心誠意こめて探究する者にとって、どうしてもその対象に愛着が出て来てしまい少なからず贔屓目で見てしまうのは仕方のないことである(私もやっぱり多少なりともインドびいきだったする)。"嫌韓"などという言葉を聞いて久しいが、人によっては揚げ足を取る人もいるだろう。
ただ、それらを除いても本書における著者の鋭敏な分析は、朝鮮半島が培ってきた思想的背景を知ろうという者にとっては多大な恩恵を残してくれるはずだ。
カラー版 - ふしぎな県境 - 歩ける、またげる、愉しめる
西村 まさゆき
出版社:中央公論新社(中公新書)
発売日:2018/05/18
県境。……
北海道に生まれ育ったものにとって、それは国境にも近い何かがある。沖縄はじめ離島出身の友人・知人らからはまた別の感情を持っているような話しを聞いたことがあるが、道産子にとっては「県境」とはそういうイメージだ。
上京したての頃の私は八王子近くの街に住んでいたのだが、散歩がてら家や畑が点々とする郊外を歩いていたら、突然『神奈川県』という標識が目に飛び込んできて心底驚いた思い出がある。
また、弥次喜多よろしく友人と鉄路で小旅行に出たところ、「山梨! 山梨! 山梨に入るよ~。ドキドキするね~」などとはしゃぐ私を見て友人に呆れられてしまったこともあった(お察しの通り中央線利用です)。
上京したての頃は「県境」とはそのくらい物珍しいものに感じたものだ。その後、仕事の関係で全国を飛び回っているうちに全く気にならなくなってしまったのが残念といえば残念だ。
青森以南の方にとっては少々理解しづらいことかもしれない。しかし、そんな「県境」という存在に慣れきった人でも本書に挙げられている様々な突飛な県境を知っているという人はどのくらいいるだろうか?
テレビで紹介されたことのあるメジャーなものはもちろん、世にいうマニアの間でこそ知られているような全国津々浦々に点在する不思議な県境を13か所選りすぐり、その県境の成立の解説、紀行文が添えられている。カラー写真が豊富なところが実にありがたい。普段デイリーポータル Zなどで執筆する著者ゆえに文章も読みやすい。
……ただし「これ、中公新書で出すべきだったの?」という感は否めない。「本が売れない」などという声を聞いて久しいが、最近、どこの新書でもこういう軽いタッチのものが増えすぎているように感じている(特にブルー○ックス)。なにもこういう書き口が悪いと言っているワケではない。こういう題材がいけないとも思わない。しかし、新書がなぜ"あの大きさであの厚さであの値段"かと考えた時、本書のような内容では少々緩慢すぎる気がしてならない。
個人的に新書には「この厚さでこんな濃厚な内容読ませてくれるの!?」という期待が少なからずあるだけに、ちょっとその辺り複雑な思いではある。
なにはともあれ、デイリーさんの方でもかなり楽しませてもらっている著者だけに、内容は実に面白い。本書を手に、秋の旅路は県境巡りというのも良いかもしれない。