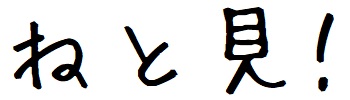バンヴァードの阿房宮
ポール・コリンズ 著
山田和子 訳
本当のことを言えば、この本を紹介しようかどうか、迷った。
なぜなら、面白すぎるからだ。
副題にはこうある
『世界を変えなかった十三人』
「こちらがメインタイトルなのでは?」とも思えるだろうか?
この本は、
精一杯の情熱を持って夢を追い続け、
ある者はその夢をかなえ、またある者は夢破れ、
しかしいずれも歴史の表舞台には名前はおろかその功績すら残らなかった、
そんな13人の偉人たちのポートレート集。
著者は言う
「歴史の脚注の奥に埋もれた人々。傑出した才能を持ちながら致命的な失敗を犯し、
目のくらむような知の高みと名声の頂点へと昇りつめたのちに破滅と嘲笑のただ中へ、
あるいはまったき忘却の淵へと転げ落ちた人々。
そんな忘れられた偉人たちに、僕はずっと惹かれつづけてきた…」
「…その栄誉を勝ち得たひとりひとりの背後には必ず、
同じ夢を追求して破れたものがいるのだということ」
死後の栄誉や称賛もなく、人口に膾炙することもない。
だがそんな彼らの姿を容易に笑い飛ばすことはできない。
きっと彼らの人生の中では、「なにかに夢中になる」という要素が大きな比重を占めていたに違いない。
結果は失敗だったのかもしれないが、
「自分の人生を精一杯生きる」
彼らはそれをやってのけたのだ。
そのことは、著者の丹念な筆致とともに、
忍耐強く資料の調査や考証を助けてくれた図書館員の方々へ捧げられた巻末の「謝辞」からも感じとることができる。
巻末の「謝辞」にはこうある
「図書館は、過去の様々な思索や営為を保存するために存在している。
こうした保存に時間をかけることのできる者は、もはや図書館以外にはない。
図書館が集めている書籍や資料は、これから十年、五十年、百年、
もしかしたら永遠に使われることがないかもしれない。
そんな不確かさこそが、図書館を、人類が創造したものの中で最も英雄的な存在となさしめている」
この本に収められた13人とともに、
彼らの歴史に埋もれたその業績を保管・保存し続けてきた図書館というものへの
最高の賛辞ともとることができよう。
ちなみにだが、種村季弘や澁澤龍彦などを好んで読まれる方にとってはツボです。
断片的なものの社会学
岸 政彦
たとえば、旅先でたまたま入ったデパートのエレベーターで乗り合わせた人がいた。
その人とは初対面。
今までも、これから先も、もちろんなんの巡りあわせもないだろう。
ただその時、同じエレベーターに乗った。
このことがなければ、その人が存在したことさえ自分は知らずにいたのかもしれない。
たまたま同じエレベーターに乗り合わせたがために、
自分はその人が存在していることが認識できた。
あまりうまい比喩ではないが、
人生というものもまた同じなのかもしれない。
小さな断片の数々。
自分の幼少期のころの思い出。
青春時代の苦い思い出。
人生はよく道に例えられるが、
もしかすると、路傍に転がる石ころを積み重ねた石塚なのかもしれない。
ひとつとして同じ形のもののない小石。
その一つを取り上げてみれば、
実はとても面白い形をしていたり、
あるいは周りに転がる石とは全く異質なものだったりするかもしれない。
この本には、市井の人々の小さな物語が、
小石を積み上げ山とするように、
ただひたすらに切り取られ、編み込まれている。
つかみどろころのない挿話の迷路。
「断片」としか言いようのない人生の欠片を、
そっと閉じ込めた宝箱のような本である。
住友銀行秘史
國重惇史
バブル期に起こった戦後最大の経済事件、“イトマン事件”。
闇社会から政財界まで巻き込んだ一大スキャンダル。
その内幕にいた元取締役による手記。
刻銘なメモに基づく事件と内部抗争の回顧録である。
著者は「私がイトマン事件当時に見聞きしたこと、
みずから体験したことはすべて墓場まで持っていくつもり」だったとしているが、
これは日本の経済史を語る上では欠くことのできない貴重な資料でもある。
事件から20年以上経ったとはいえ、いまでも当事者の多くが存命の中、
よく上梓したものだと思った。
ただ、著者本人もこの事件の中心にいた人物である以上、
杳として知れないその全貌を見つめた“一視点”であることは忘れるべきではない。
読み終えて、正直消化不良を起こしそうだった。
テレビドラマで観るようなおぞましい人間関係、
足の引っ張り合い、闇社会とのつながり…
それらすべてが現実に起こりえたことの衝撃はもちろんだが、
この事件で流れ出た巨額の資金の行方が今もって不明ということも更に拍車をかける。
バブルという時代は「カネになりそうな話なら一流企業からヤクザまで、
誰でもすぐにとびついて、儲けようと虎視眈々となっていた」
そんな時代の話し。
このかつての一大スキャンダルの内幕から、
今の私たちは何を学びとれるだろう?
僕の叔父さん 網野善彦
中沢新一
「偉大な歴史学者の網野さんは、僕の素敵な叔父さんだった。」
なんと心安らぐ本だろうか。
2004年、日本の歴史学に新たな一矢を加えた歴史学者・網野善彦が逝去した。
当時、数多くの著名人の手でその死を悼む追悼文が世に出たが、
この本は、叔父と甥という関係以上に濃密な時間を共有しえた著者をして綴られた「ものがたり」である。
その思慕、尊敬、なつかしい思い出が込められた好著だ。
いろいろ書こうとは思ったのだが、
余計な言葉は控えておこう。