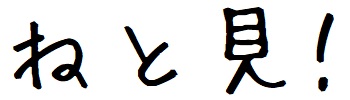あれか、これか――「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門
野口真人
出版社:ダイヤモンド社
発売日:2016/04/22
副題にある「ファイナンス理論入門」という言葉通り、ファイナンス的思考を学ぶ初歩には最適な一冊。
基本的な思考から「なぜそうなるのか?」「(ファイナンス的には)こう考える」ということが丁寧かつやさしく解説されている。
しかし個人的にはあまり真新しいことはなかったかなという印象を抱いている。
というのは、本書ではお金をはじめとしたものに置かれる「価値」ということを基軸に、判断するための基準、リサーチの手段などのファイナンス的思考・方法論が語られているが、そもそもお金に対する教養をある程度身に付けている人にとっては、ごくごく当たり前の話しのように思うからだ。お金の教養というものもファイナンスの一つなのであろう。
本書で語られるファイナンス的思考の第一歩は、価格と価値を分け価値の見極めを重視することにはじまる。そしてその価値を現状の市場価格やコストで計算するのではなく、お金の流れ(本文中では「キャッシュフロー」といっている)の中で決める。つまり将来的にどれだけのキャッシュフローを生み出せるかが最大の関心事で、そのキャッシュフローの総額が大きいほど価値が高いといえる、というのだ。
これを自分たちの日常生活に置き換えてみると分かりやすいかもしれない。甘いものを食べたいと大量にお菓子を買ったとする。それを買って食べることで一時的な満腹感なり幸福感なりを手にすることはできるが、そこで支払ったお金は結果食べることで消費されるばかりだ。一方同額の支払いを資格試験の問題集にしたとする。それを使って勉強し資格を取るとすると、結果仕事などに繋がり、収入となって返ってくる。この場合、同じ金額を支払ったとはいえ後者の方が潜在的に多くの富を得られる、生産性があるということになる。つまり、同じ金額のお金でもそれが内含する価値が(将来的に)違うということだ。
これを幾度も繰り返していると、将来的にどちらが富、お金を中心とした資産を多く築けるか容易にわかるだろう。
ただし一つ気を付けなければならないのは、これが「ファイナンス」に関して書かれた本であることだ。
会計的には流動性比率の高い「現金」に一番の価値をおくが、ファイナンス的には「現金」の価値は一番低い。そして「価値」と「価格」を分けながらも、最終的には「価格」に換算しなければならない矛盾がある。これがある意味ではファイナンスの面白い部分であり、またとても人間臭いものだということに気づくだろうか?
資産運用や株をはじめたいという人はもちろん、「本当の値打ち」とはなにか知りたいという人にとって、ファイナンス全般を網羅的に把握するためには近年稀にみる良書であることは間違いない。
ラカンの哲学 哲学の実践としての精神分析
荒谷大輔
出版社:講談社(講談社選書メチエ)
発売日:2018/03/11
21世紀を代表する精神分析家ジャック・ラカン。その理論の難解さは生前もしばしば批判を浴びていたが、本書裏には「難解晦渋で容易に人を寄せつけないその思想は、しかし『哲学』として読むことで明確に理解できる」と書かれている。
精神分析は哲学であるか否かという議論はフロイトの昔よりしばしば取り沙汰されてきたが、個人的な見解をまず書けば、精神分析も十分哲学であると思う。そもそも哲学というものはとてつもなく大きな器のようなものだという認識があるので、その一分野に精神分析学というものも十二分に含まれる余地はあると思う。
本書ではフロイト以降、その業績を継承・昇華することで精神分析学に新しい思想的境地を開いたラカンの思想体系を、年代順に代表されるテーマに焦点を当てて解説されている。
著者曰く「明確に哲学の立場」をとるために「ラカンの原典を読み、二次文献で語られていることをあたかもラカンが語るかのように扱うことも控える」としている。哲学研究の手法としては実に凡庸であるが、精神分析、殊ラカンに関しては「意外に少ない」のだという。ただ、この点が実は本書の欠点になっている気がしてならない。
というのは、ラカンの思想を解説したものという観点からだとその数は多くあり、本書もその中の一つに埋もれてしまいかねないという懸念があるからだ。もちろん原典から直接その思想を読み解くことは大変重要であるし、一人の哲学者・思想家を知る上では欠かせない作業だ。しかし本書では結果的に著者の言わんとすることが、読み進めるうちに不明瞭になってくる。「あとがき」で「(人間の欲望の向かう先をより良いものにする契機を少しでも多く確保するために)ラカンのテクストを読む可能性を示した」と書いているが、冒頭の序で書いてあった目的と少しズレがあるような気がするのだ。また、「難解」といわれるラカンの哲学の「難解」たる部分の解説も、やっぱり少し分かりづらい。ラカン自身数学記号を用いるなどしているため、数学的立場と(精神分析を含む)哲学の立場とでその意味合いが正しく共有されていないことも相俟って、余計に混乱をする。……
と、いろいろ批判めいたことを書いてはいるが、実際にラカンの哲学に触れる上では、原典と直接渡り合ってくれていることから、入門書としては十全だと思う。もちろん、哲学ないし精神分析学に関しての基本的な知識があった上での入門である。まったく予備知識のない人が読むには少々敷居が高い。
 享楽社会論: 現代ラカン派の展開 |
 疾風怒濤精神分析入門 ジャック・ラカン的生き方のススメ |
しししのはなし 宗教学者がこたえる 死にまつわる<44+1>の質問
正木 晃・著 クリハラタカシ・イラスト
出版社:CCCメディアハウス
発売日:2018/08/01
著者はチベット仏教を修めた宗教学者だ。
本書では「死」ということを基軸に、仏教に限らずさまざまな宗教の視点を取り入れたり、宗教的なもの自体を排除した著者自身の感想があったり、硬すぎずゆる過ぎず、しかし絶妙な筆致でその命題に対する多角的なアプローチをおこなっている。アニメや小説、医学的データやアンケートデータなど、分かりやすい事例を用いられていてとても読みやすい。
「死」とはなにか? 「死」ぬとどうなるか? 他人の「死」と自分の「死」の違いは何か?
古来より幾多の人々がそのことを考察しつづけてもなお答えの見えない「死」。生きとし生けるもの全てに平等に訪れる「死」は、それ自体一つの概念でありながらそれとの出会い方は千差万別だ。
浄土真宗第8世・蓮如の『御文章』の名筆「白骨の御文」には「……いまにいたりて、たれか百年の行体をたもつべきや。我やさき、人やさき。けふともしらず、あすともしらず、おくれさきだつ人は、もとのしづく、すゑの露よりもしげしといへり。されば、朝に紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」(『蓮如文集』岩波文庫p238)という有名な一文があるが、まさしく、生きているということは常に死と隣り合わせなのだ。それは寿命であったり、病気であったり、事故であったり、あるいは自死であったり……だが、「死という鏡に照らし出されて、生は初めてその本当の姿をあらわすはず」という本書中の言葉がある意味真理であるように思う。
本書には、巷で言われるような「死ぬとき何が見えるか?」「あの世はどんなところか?」というメジャーな疑問から「動物たちは死を考えるのか?」「死んだら結局みんな同じなのか?」といったかなり複雑な話しまで、それぞれに平易で分かりやすく、それでいて真摯な回答が与えられている。もちろん、それが正解なのか否かはわからない。わからないからこそ考えねばならない。
元来、お盆あるいは年忌法要といった仏事・神事、その他宗教行事はそうした「死」を迎えた故人を通し、今を生きる人々が死とは何かを考える機会であったはずだが、昨今の世相の変化によってそうした意味合いもかなり薄れてしまっていること、更には社会全体が「死」というものをタブー視したかのように日常生活の中から意識的に遠ざけてしまっているような気風を感じるが、実に遺憾なことだと思う。そしてなにより、宗教というものに対しての胡散臭さや過激的なイメージが更にそれに拍車をかけてしまっている感があるのは、本末転倒以外のなにものでもない。
宗教というものは、今では儀礼的行事的なまったく形骸化した例も多くないが、それが宗教の本来の姿ではない。個人的に、宗教というのはもっとシンプルで知的なものだと思う。つまり、死者と生者をつなぐ架け橋であるはずなのだ。それをある宗教では神を基軸にし、またある宗教では仏を基軸にし、またある宗教では契約を基軸にしている、そんな差異でしかないように思うのだ。
本書中に紹介されていた言葉だが、これは非常に大切だと思うので紹介しておきたい。幽霊がいるかいないか、またもし見てしまったらという部分で引用されていた、東日本大震災の被災者の支援に関わる僧侶の金田諦應氏の言葉である。
「(幽霊が)いる、いないは別にして見ているのは事実。みな、心の構えがないまま多くの人を亡くした。親族や仲間の死に納得できるまで、上を向けるようになるまで、宗教が辛抱強く相談に乗っていくしかない」
宗教の基本的な部分である信仰というのは、言い換えれば「なにかを信じきること(信念)」だ。それが宗教でなくてももちろん言いわけだが、宗教というものが持つ力は、その人に何かしらの答えを自ずから見出させるためのものだと思う。
いつか必ず誰しもに「死」はやってくる。そしてそれは常に「生きている」ことの傍らにある。そのことだけは忘れてはいけない。
はじめての宗教学
『風の谷のナウシカ』を読み解く〔新装増補版〕
大家さんと僕
矢部太郎
出版社:新潮社
発売日:2017/10/31
昨年秋に出版され話題を呼んだエッセイ漫画。
お笑いコンビ・カラテカの矢部さんと彼の住むアパートの大家さんとの心温まる話しの数々。
話題になっていたのは知っていたけど、ついつい読みそびれてしまっていて先日やっと読んだという不覚。
そして更に不覚にも、読み進めていくうちになんだかほっこりと心温かくなって、気が付いたら目に涙を浮かべていた次第。二人のやりとりは、いい歳したオッサンの心にも十分響いた。
矢部さんはテレビでよく見るだけにその人柄も周知のものと思うが、その彼が語る大家さん像がまたなんとも人間臭くてとても好感が持てた。
第一声の「ごきげんよう」にはじまり、矢部さんのことを心配するあまり洋服を取り込んだりなんだり……。そんな大家さんの言動に最初のうちは戸惑っていた矢部さんだが、次第に二人の距離が縮まっていくさまには、昨今の日本人が忘れかけている大切な何かがあるような気がした。
以下、若干ネタバレが含まれてしまうが、伊勢丹が大好きな大家さんと二人でランチをした際予想以上に豪華だったがために度肝を抜かれたり、センサー式のライトを取り付ければ、大家さんが通るたびにいつも矢部さんが点けたり消したりしてくれているものと勘違いされたり、歳の差があるのだから当然といえば当然だが、そのデコボコ感がなんとも優しい時間を演出している。
しかしその中でも、品の良い穏やかな大家さんの全ての基準が「戦争」であることは考えておかなければならない。終戦時17歳だったという大家さんは、矢部さんを見て「なんで日本が戦争に負けたかわかる気がするわ」と冗談めいたことも言ったりするが、その実、疎開中から今なお交流のある友人たちの話し、戦時中の話しなど、決して暗くはならないエピソードばかりだけれど、あの大事が大家さんの心にどれだけ大きなものを負わせたのか、身につまされる思いだった。
今年8月、この大家さんの訃報のニュースがあった。
cf,「8月が特別な月になった」大家さんを見送った矢部さん:朝日新聞デジタル
当時の記事を読むと、矢部さんと大家さんとの信頼関係の厚さが手に取るようにわかる。
世代間のギャップには身内でも埋まりきらないものがあるが、それを通り越したこのほのぼのとした経験は、矢部さんの人生にとって大きな糧となっただろうし、読者にもその「おすそわけ」を与えてくれる。